
メンタルトレーナーの葉月です。
今回のテーマは 「スポーツをする子供の思春期・反抗期」についてです
昨年より中学バスケットボール部のメンタルトレーニングに携わるようになって、同じ子供でも小学生と中学生ではやはり全然対応が変わってくるなと感じることが多々ありました。
子供達は中学生になることによって、先輩・後輩の「縦社会」を経験することになり、同時に自立したいという感情が芽生える時期でもあります。
特にこの時期の子供達は、お母さんやお父さんに反抗的な態度を見せることがあるため、親は動揺して「子供が望まない行動」をしてしまうことがあります。
その結果、子供が心を閉ざしたように親を無視したり、きつい言葉を投げてきたりするわけですが、このような状態が幸せだと子供も思ってはいません。
今回は 「スポーツをする子供の思春期・反抗期|親はどう向き合うべきなのか?」について考えていきたいと思いますので、最後までお付き合いいただければと思います。
思春期の心

思春期を迎えた子供達に「何を考えているのか分からない」「昔はあんなに素直だったのに」と親は戸惑いを隠せないことが多くなり、中には「自分の育て方が間違っていたのか」「自分の愛情の注ぎ方が間違っていたのか」と保護者の方が思い悩んで健康を損なってしまうということがあります。
しかしそれは子供が成長している証拠ですし、いつまでも親が絶対的な存在であり続けることは、子供自身が自立した大人になるための妨げとなってしまいます。
私達大人もそうだったはずです。
思春期になると、親が嫌いになったわけでもないけれど、なぜか疎ましく感じて、親の言っている事に対して疑問を抱くようになったことはありませんか?
そして親よりも、「友達」「先輩」「先生」「顧問」といった他人の方がずっと親しく感じられたり、親の意見には反発したくなるけれど、先輩や顧問に言われたら受け入れるなんてことは多々あります。
ただこのような状態がずっと続くわけではありません。
子供達が親と距離を置くことで「自分自身の価値観」を確立することができれば、親も「1人の人間」として子供の中に位置付けられますので、そうなれば思春期や反抗期が終わりを迎える時です。
ただこの時期の接し方によって、子供達の思考や価値観を大きく左右してしまうことがありますので、お父さんやお母さんは子供の「自尊心」「自己肯定感」など成長に欠かせない感情を摘み取らない言動をすることが必要となります。
他人には言えて親には言えないこと
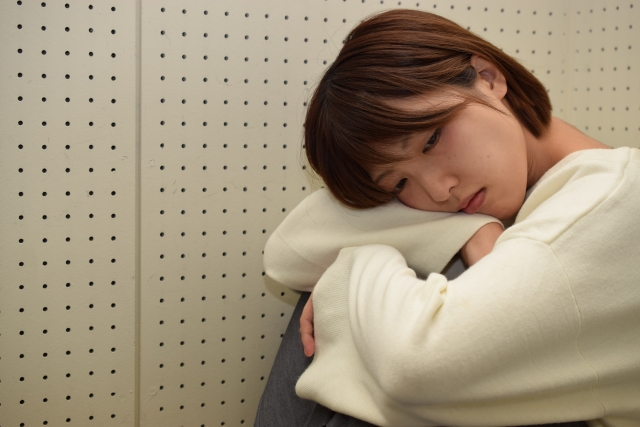
私が中学の部活動生徒に行うカウンセリングで、親には言えないことを私にはすんなり言ってくれるってことは多々あります。
「親には言えない」というよりは「親には言いたくない」という方が正しいかもしれません。
先日も女子部員が練習をサボるようになったので、その子のお母さんから相談の連絡をいただきました。
「サボることはみんなに迷惑もかけることだし、行くなら行く、行かないなら部活を辞めて勉強1本で頑張る、どちらかを選びなさい!と美奈に伝えたんですが、“部活に行こうが行くまいが私の自由だし、勉強しなさい勉強しなさいっていちいちうるさい!”って言われてしまって…。皆さんには心配とご迷惑をお掛けして本当に申し訳ないです。本人にはきちんと答えを出すように言ってありますので、もう少し待ってもらえませんか?」
ということでした。
その翌日その女子部員と話をしたのですが、部活をサボるようになったのは先輩とのトラブルが原因でした。
グループラインでちょっとした誤解が生じ、それから顔を合わせることが怖くなって部活をサボるようになったようで、本当のところはバスケがしたくて部活に戻りたいとの気持ちを話してくれました。
お母さんはとても心配してるし、その事実をどうして打ち明けないのかを聞いたところ、「いつも決めつけた言い方をするし、以前友達から集団無視をされて相談した時も「そんなの時間が解決するわ」「それよりも今は勉強を頑張らないと」自分の話を聞いてくれなかった時のことを思いだして、親に本当のことを言う気にはなれなかった。」とのことでした。
このように親はどうしても子供達の将来のことまで見越したアドバイスや言動をしたり、周りの目を気にして子供自身が抱えている悩みが曇って見えないケースがあります。
しかし、私が向き合っているのは「今の子供自身」なので、子供達は安心して色々と話してくれるのですが、私も自分の子供の事となると、そうはいかない時もあるので美奈ちゃんのお母さんの気持ちはよく分かります。
だからこそ周りに頼ることは大切だし、第三者の手を借りながら子育てをしていけばいいと思うのです。
それは決して子育てに手を抜いているのではなく、子供が望んでいる環境を提供しているに過ぎませんし、子供が心を開ける人が周りにいることはとても幸せなことではないでしょうか。
反抗期って必ず来るの?
小学生までは親の言うことを素直に聞いてきた子供達も、「自分がしたいこと」や「自分の考え」を大事にしたいという思いが芽生えてきますので、今まで親が絶対的な存在だったけれどそうでなくなるため反発をし、それを「反抗期」と呼んでいますが、「うちの子には反抗期がなかったのよ」と言うお母さんもいらっしゃいます。
子育て論や教育論が書かれている書籍を見ると「反抗期がない方が問題」なんてことが書いてありますが、これも一概にそうとは言えません。
親が子供に反抗することは当たり前だし、そんな子供と上手に向き合っているお母さんはそんな時期を「反抗期」だと捉えることなくこの時期を通り過ぎすぎているなと感じます。
一方で問題とされているケースは、学校生活の中で分かったりします。
家庭の中で反発することが許されない状態を親が作ってしまえば、子供は家の中で思春期・反抗期を迎えることができず、学校内で「イジメ」などの問題を起こしてしまうことがありますし、最終的に「非行」へ走ってしまうケースもあります。
子供の反抗期を目の前にした親は、時として自分を責めてしまったり、子供に「劣等生」のレッテルを貼ってしまうことがありますが、反抗期は誰もが通る道。
それを辛く感じてしまうのは、「乗り越えなければならない」と考えるからで、子供が話しかけて来た時はきちんと最後まで聞いてあげて、子供の機嫌が悪い時はそっとしておくこと、ただそれだけです。
ただし、腫れ物に触るような言動は逆効果になりますので、あくまでも親は今まで通りの態度で、ただ「口うるさく言わない」これが鉄則のような気がします。
子供の成長に合わせた対応を

小学生からスポーツ少年団やクラブチームでスポーツをしていた子供の成長に、親がついていけていないケースを時として見かけます。
「〇〇君、いいよ〜!その調子!!」と親からの声援を嬉しく思っていた子供達も、中学生になるとそれが「恥ずかしい」と感じるようになります。
異性の目も気になりだす思春期の子供達にとってはそれが当然の反応かもしれません。
そのことが良いか悪いかは置いといて、このように子供達は日々成長しているわけですから、親も子供に対する対応を変えていくことが必要なのは当然のことかもしれません。
子供との関わり方や距離の保ち方を考えることも大切ですし、子供が掲げた目標や夢を批判することは挑戦する意欲を奪うことになりますし、これからは子供の意思を尊重してあげることも重要で、「それは絶対に無理」だという内容に対しても、子供の話を遮らず最後まで聞いてあげることが大切です。
まとめ
今回は 「スポーツをする子供の思春期・反抗期|親はどう向き合うべきなのか?」についてお伝えしましたがいかがでしたでしょうか。
私も子供達の反抗期には、頭では「思春期」と「反抗期」の大切さを理解していても、実際目の当たりにすると戸惑うことも多くありました。
しかしこの時期がなければ、子供は自分で考えて自分から自立していくことができませんし、いつまでも親に依存していては本当の自分を見つけることができずに、年齢だけが成人を迎えるということになってしまいます。
子供の成長に合わせて大人達もその時その時で、対応を考えていく必要があるのだと思います。

