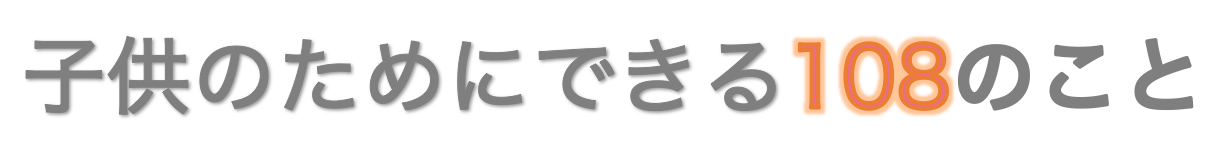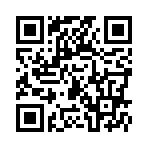子供のメンタル強化は指導者で左右される!トレーニングの落とし穴

メンタルトレーナーの葉月です。
今回のテーマは「子供のメンタル強化と指導者が行うメンタルトレーニングの落とし穴」についてです。
子供達にはそれぞれの個性があって、「我慢強い子」「温厚な子」「マイペースな子」「落ち着きのない子」「負けず嫌いな子」「ひょうきんな子」「おとなしい子」など色々なタイプがありますが、私が子供達へメンタルトレーニングする目的は、どの子供にも例外なく「目標を達成させる」ことにあります。
しかし指導者が「目標を達成させる」ことばかりに意識を向けてしまうと、不本意ながらそれが子供にとって逆効果に作用してしまうケースがあります。
メンタルの深意を分かっているような分からないような…と言う人はとても多いし、分かった気で子供達の心を鍛えようとすることはとてもリスクが高いことです。
そこで今回は 「指導者が気をつけたいメンタルトレーニング5つの注意点」についてお伝えしたいと思いますので最後までお付き合いいただければと思います。
威厳に対する履き違え

人が誰かに何かを指導する時、それに対する知識や経験を必要としますし、自分自身が常に学ぶ姿勢を大切にしなければ、子供達もそれに応えてはくれません。
子供達が指導を受ける際は「何を学ぶか」「どこで学ぶか」よりも「誰に学ぶか」の方が重要視される傾向にあります。
同じことを言われても、自分が信頼している人に言われるのと、そうでない人から言われるのとでは、受け取る側の思考は大きく左右されるため、結果にも大きな差が生じます。
そしてコーチも無意識にそのことを認識しているため、子供達に対して「信頼される」「威厳を保つ」ことが必要だと考え、自分なりに威厳のある振る舞いをしようとする方がいらっしゃいます。
ただ「偉そうに振る舞うこと」と「威厳を保つこと」は全く別物ですし、そこに暴言や暴力が存在することは絶対にあってはなりません。
威厳の意味を履き違えて、上から偉そうに指示を出すだけでは、子供達が信頼を寄せるはずがありませんし、一方的な指導では子供達の「自主性」「主体性」「意欲」を育てることは難しいでしょう。
威厳とは「近寄りがたいほど堂々としておごそかなこと」という意味を表わす言葉ですが、この言葉には「尊敬に値する」といった含みの意味も存在します。
子供達から信頼されるには、まずは自分が子供達を信じることが大切ですし、子供達から尊敬されたければ、まずは自分から子供達を尊敬する心を持つことが大切です。
暴力的行為は犯罪です!
指導者が選手へ「殴ったり」「蹴ったり」することが、指導の一環だとされ周りから黙認されている時代もありましたが、その風習を現在も引きずっている指導者は少なくありません。
強豪チームになればなるほど、その傾向は強く、昨年も「少年野球監督の平手打ち事件」が明るみになり、大阪府の少年軟式野球協会と軟式野球連盟は、当事者である監督を無期限の活動停止処分としました。
このチームは、練習中にも暴言や暴力が日常的に使われていたようですが、自分の指導下にあるからと子供達へ暴言や暴力を使っていいことにはなりませんし、このような振る舞いは紛れもなく「傷害罪」です。
傷害罪は「相手に怪我をさせたらその罪が成立する」というイメージがあるかもしれませんが、例えば精神的苦痛を与え続けて相手がうつ病になっても傷害罪になります。
それをグランドだから許される、コート上のことだから許されるということは絶対にあり得ません。
道ゆく人を平手打ちにすれば、当然警察沙汰ですし、普通じゃないですよね。
それが「自分は指導者だから」「相手が教え子だから」などといった理由で、子供を服従させようとすることは、誰も幸せでないし、そこで得た勝利がそれほど価値のあるものか疑問でなりません。
暴力が有能な選手やチームを育てたというのなら、暴力を使わないで有能な選手やチームを育てるように考えることが指導者がするべきことではないでしょうか。
合わせて読みたい史上最低!ミニバス指導者のテクニカルファウルで逆転負け
選手・チームが伸び悩む原因とは

私のところへメンタルトレーニングの相談へ訪れるコーチや監督は、とても指導熱心な方が多く、常に子供達のことを第一優先に考えている方が多くいらっしゃいます。
しかし、それでも選手の伸び悩みやチームの伸び悩みに直面し、「自分の指導は本当にこれで正しいのだろうか」「本当に子供達のためになっているのだろうか」「どうして成果が出ないのだろうか」と悩んでいる指導者の方も少なくありません。
そうなる場合に最も多く見られる原因は「子供のことを理解しているようで理解できていない」「子供のことを見ているようで見れていない」という状態があげられます。
指導する側が何かの知識を得て、それを子供へ伝える時「自分ファースト」になっている場合があります。
自分が得た知識や経験の全てを伝えることだけがあなたの目的であれば、私が言うことは何もありませんが、そのことを本当に子供達へ理解してもらいたいと思うのであれば、まずは指導をする側が子供達の心を理解することが大切です。
子供の心を無視して、子供の心を一方的に強化しようとしても、マイナスに作用するばかりでプラスに作用することはまずありません。
たとえばバスケを始めたばかりの子に、いきなりバックシュートを習得させようなんて思いませんよね。まずは「基本姿勢」の習得から始め、ハンドリング、ドリブル、パス、キャッチ、ステップ、シュートなどのように段階的に指導して基本からしっかり教えてくと思います。
それはメンタルトレーニングも例外ではありません。まずは子供の心の安定が第一優先で、それぞれが持つ「弱み」「強み」をしっかり把握したうえで色々な角度からのアプローチが必要となります。
メンタル強化は「体」と「技」を強化することにもつながりますが、そのことばかりに意識を向けてしまうと、どうしても「焦り」が生じて結果を早く求めてしまうことになります。
メンタルトレーニングは競技能力や体力と同じように、すぐに成果が出ることはありませんし、基盤をしっかりつくってあげなければ、長期的に活躍できる選手を育てることはできません。
子供のモチベーションが保てない原因

子供達のやる気を高める方法は大きく分けて2つあります。
一つは褒美や罰を与えることでやる気を高めさせる「外発的動機づけ」で、もう一つは褒美や罰に関係なく自分がしたいからそうするという「内発的動機づけ」です。
外発的動機づけは、手っ取り早く結果につなげさせることができるため、指導者はこの方法を使いがちで、練習中に「やる気がないなら帰れ!!」とその場を立ち去って子供達にこれからどうするべきか考えさせることも外発的動機づけの一種です。
指導者は自分達で考えて行動する「主体性」を育てたいと考えているのかもしれませんが、子供達は「コーチが怒っているから、自分達がダメだった点を伝えて謝ろう。」と考えるだけで、指導者が本当に求めていたものが得られているとは思えません。
意欲的に練習へ取り組むために必要なモチベーションは「コーチに怒られるから」ではなく「自分達が強くないたいから」という「内発的動機づけ」を動かすことです。
そのためには、日頃から子供達が「達成感」を得られるような目標設定や、指導者が暴言や暴力を使わない指導が大切だと言えるでしょう。
達成感が諦めない心を育てる
 スポーツをしていれば、色々なチームや選手と対戦する機会があると思います。中には「どう考えても勝ってこない」と後ずさりしてしまうような、強豪チームと戦うこともあるでしょう。
スポーツをしていれば、色々なチームや選手と対戦する機会があると思います。中には「どう考えても勝ってこない」と後ずさりしてしまうような、強豪チームと戦うこともあるでしょう。
しかし、その強豪チームを相手にベストを尽くして決めた1ゴールは、子供達にとって将来を支える「達成感」へとなってくれるはずです。
例えば、自分達よりも弱いチームに100対0で勝った試合と、自分達よりも強いチームに24対48で負けた試合とでは、どちらが子供達の自信やエネルギーとなるでしょうか。
もちろん力の差があれば、できないこともあるでしょう。しかし、圧倒的な能力・技術の差がある中でも、 自分ができる「最大限のプレー」をすることができれば、負けた試合でも子供達を大きな成長へとつなげてくれます。
褒める時の注意点

子供達には「怒る」ことよりも「褒める」ことが良いとされ、スポーツ指導でも褒めることが重要だと言われています。
しかし褒めすぎることで逆効果になってしまうことがありますので、指導者はその点にも気をつける必要があります。
それは、褒められなければ「自分は期待されていないのか」「自分は失敗したのか」「これは間違えなのか」と子供達を不安にさせ、褒めて伸ばすつもりが「褒められなければ意欲が沸かない」「褒められなければ行動できない」という状態をつくってしまうことがあるということです。
子供達を褒めるうえで大切なことは「結果」ではなく「プロセス」や「努力」に対しての言葉かけで、子供達が自分で考えて行動をさせるためのサポートをしてあげることです。
合わせて読みたいスポーツで「褒めて伸ばす」の目的とは|自己肯定感の育て方
健康な体であることが基本
 安定したメンタルを保つには、健康な体であることが必要です。
安定したメンタルを保つには、健康な体であることが必要です。
子供の成長を無視した練習量やハード過ぎるトレーニングを行い、オーバーワークになってしまえば、健全な精神は保たれません。
「辛い練習に耐えることが精神力を鍛えることにつながる」とおっしゃる指導者の方がいますが、成長期の子供達の健康を犠牲にする行為はスポーツとは言えません。
もちろん指導者による「暴言」「暴力」は絶対にあってなりませんし、競技能力を上げるには健全な精神力が、健全な精神力を保つには健康な体が必要だということです。
まとめ
今回は「子供のメンタル強化は指導者で左右される!トレーニングの落とし穴」についてお伝えしましたがいかがでしたでしょうか。
子供がメンタルを強化するためには、メンタルが安定していなければいけませんし、子供のメンタルを安定させるためには、周りの大人達がイライラしていたり、何か別のことに気を取られていては、大人が望むそうな答えは返ってきません。
相手を理解するためには、自分自身の心理状態を把握しておきことは必須ですし、指導者が自分の思いを一方的に伝えているだけでは不十分だと言えるでしょう。